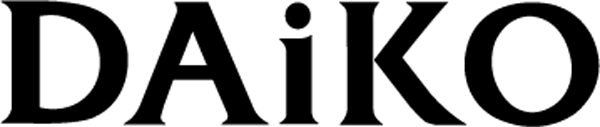– 目次 –
1.山間地での設置が増えてきた太陽光発電パネル
2.共通の目標のもとに新システムを構築
3.認知度を上げ、多くのお客さまに使ってもらいたい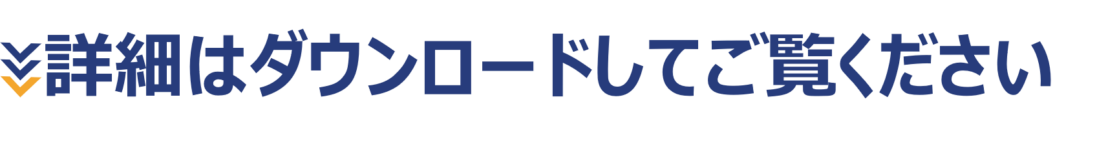
PROBLEM 3次元スキャナーで計測した土地の地形データを読み込み、最適な太陽光パネル架台の配置を自動的に計算して画面に表示する、「太陽光パネル自動配置システム」の開発
傾斜地でも整地を行なわず、画面上で最適な配置を確認。
採算性についても提案が可能

COMPANY INFORMATION
愛知金属工業株式会社様
- 業種 製造業
- 部門・業務 設備・保全
愛知電機株式会社の関係会社として設立された後、中部電力株式会社の関係会社となって送電用鉄塔の設計から製作を主業務に成長してきた愛知金属工業株式会社。
鉄塔設計で培った強度計算技術を応用し、太陽光発電用架台を効率的に配置するために開発された「太陽光パネル自動配置システム」の、導入の経緯と効果について話を伺いました。
導入による効果
-
前例のないシステムを形に
ニッチな分野で活用できる、これまでに前例がないシステムを構築。
-
業務効率化
外部データ連携とパラメータ設定だけで、人間には不可能な精密計算を自動化。
-
お客さまに投資効果を提案
投資による効果を事前にシミュレーションし、お客さまに提示可能。
INTERVIEWインタビュー
DAiKOの想い
いつでも様々な要望を伺えるよう関係性を深めていきたい
田中 卓美
名古屋支店 製造営業部
今回は愛知金属工業様が、10年前から導入していたiCADSXをベースに、DAiKOのノウハウを盛り込んだシステムになりました。今後もお互いのノウハウを生かしたシステム開発で、ご支援していきたいと思っています。
企業情報

| 社名 |
愛知金属工業株式会社 |
| 会社概要 |
1957(昭和32)年に愛知電機株式会社の関係会社として設立(旧社名:愛知製缶株式会社)。 送電用鉄塔、温水ボイラーをはじめとする金属製品を手がけるとともに、設計、製造の技術力を生かし、鉄塔診断、保守コンサルティング、太陽光発電架台などの事業を展開している。 |
本社 |
愛知県春日井市 |
| URL | http://www.aikin.co.jp/ |