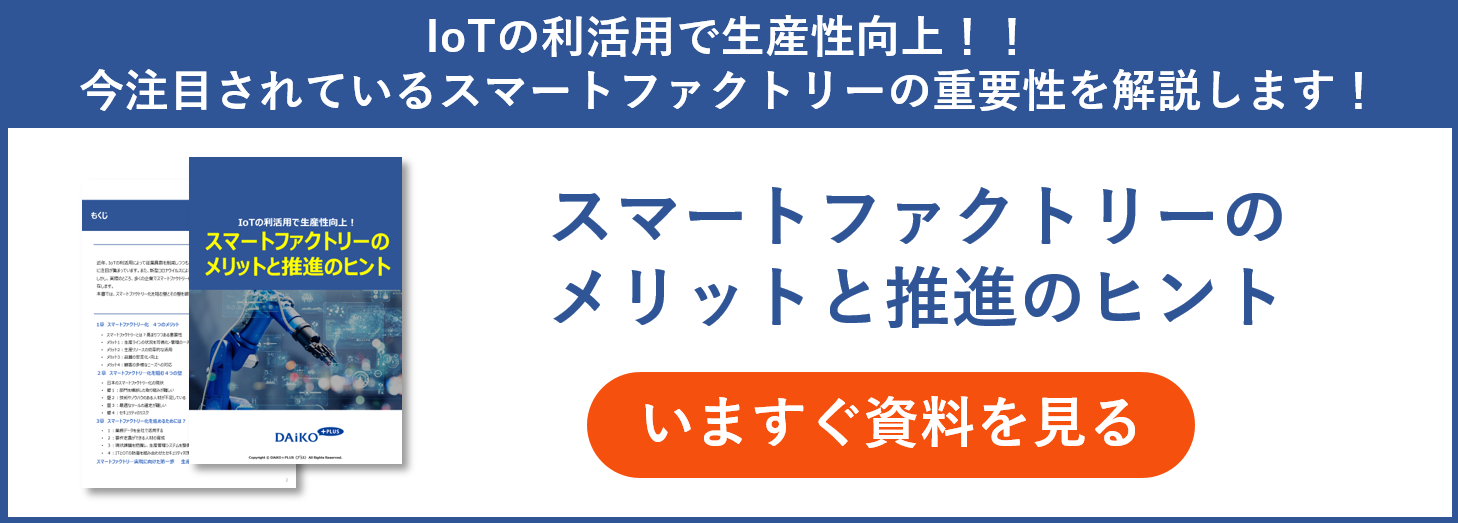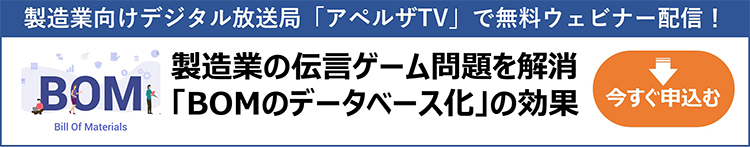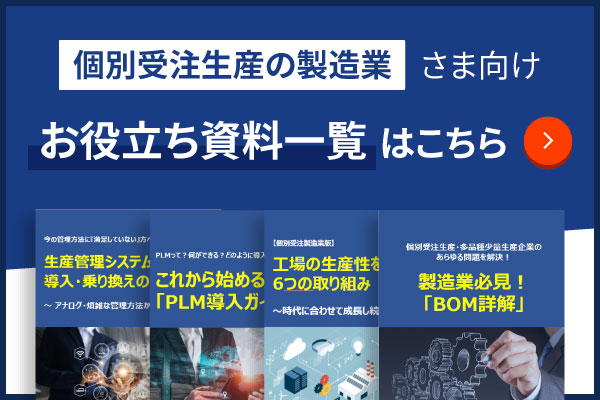スマートファクトリーとは、デジタル技術の活用により業務プロセス改善や品質向上、生産性の最適化を実現している工場のことです。製造業で注目されているスマートファクトリーですが、企業は実現に向けて何から取り組めばいいか分からないのが実態です。
本記事では、スマートファクトリーのメリットや実現するために必要な取り組みについてご紹介します。
ページコンテンツ
スマートファクトリーとは?
スマートファクトリーとは、IoTやロボット、さまざまなデータなど、デジタル技術の活用により業務プロセス改善や品質向上、生産性の最適化を実現している工場のことです。
コロナ禍の影響を受け、これまで対面でのやり取りが前提となっていた工場では、感染リスク低減のため生産の停止を余儀なくされました。それにより、サプライチェーンの中で部品の入出荷が乱れ、大きな分断が発生しました。
スマートファクトリーは、これまで人手を介して行われていた業務をデジタル化し、対面でのやり取りを最低限に抑えており、コロナ禍において大きな注目を集めています。業務のデジタル化を実現する具体的な手法としては、生産ラインの自動化や生産設備の異常検知、設備機器の予知保全などが挙げられます。
コロナ禍における日本でのスマートファクトリー推進状況については、こちらの記事をご覧ください。

実現の第一歩とは?
スマートファクトリーとインダストリー4.0
インダストリー4.0はドイツ政府が進めている国家プロジェクトで、製造業界全体の徹底した効率化と高品質化を実現し、国際競争力を高める取り組みです。「第四次産業革命」という意味合いを持ち、インダストリー4.0を実現するための主要な取り組みとして、スマートファクトリーが位置付けられています。
日本では、2017年に経済産業省が発表した「スマートファクトリーロードマップ」で注目を集めており、製造現場のデジタル化やソフトウェア化が求められています。
一方、欧州では2021年に欧州委員会が発表したインダストリー 4.0に代わる新たなコンセプト「インダストリー 5.0」が提唱されています。既存のインダストリー 4.0のコンセプトを人間や社会・環境の観点で補足・拡張した内容で、「人間中心」「持続可能性(サステナブル)」「回復力(レジリエント)」をキーコンセプトとしています。
開発競争の激化や人材不足の深刻化に苦しんでいることが挙げられ、スマートファクトリーが有効な選択肢の一つとなっています。そこで、ここからはスマートファクトリーの具体的なメリットを解説します。
スマートファクトリーの3つのメリット
スマートファクトリーのメリットには、見える化による生産性向上や、長い年月をかけて培われてきた技術の継承、リードタイムの短縮などが挙げられます。
メリット1:製造工程の見える化による生産性向上
製造工程にセンサを設置すれば、工程に関するさまざまなデータ収集や分析が可能になります。その結果、製造工程を見える化できるため、工程のボトルネック特定や作業の分担を変更でき、生産性の向上につながります。
メリット2:職人技術の継承
近年、製造業では現場で働く人材の採用が難しくなっており、その影響で経験豊富な職人の高度な技術を継承するのが困難になっています。職人の技術をデジタル技術でデータ化すれば、習得が難しかった勘・コツの部分が可視化され、後継者は効率的に技術を習得できます。
メリット3:リードタイムの短縮
さまざまな情報をデジタル化すれば、情報共有をリアルタイムかつ迅速に行えます。情報をスムーズに共有できることで、異なる部署間の連携がスムーズになり、生産リードタイムを短縮できます。また、最適な生産計画を立てることが可能になり、人材や部品のリソースを最適に配分できることもリードタイム短縮に寄与します。
スマートファクトリー実現により、ここまで紹介してきたさまざまなメリットが得られます。そこで、実際にスマートファクトリーを実現するためには、どのように進めればいいか、その流れを解説します。
スマートファクトリーを実現するためには?
自社で抱えている課題の解決を目的としてスマートファクトリーを実現するためには、以下のような手順で進めましょう。
ステップ1:解決したい課題の明確化
まず取り組むのは、自社工場において解決すべき課題の抽出です。解決手段にとらわれず、できるだけ広い範囲から網羅的に抽出し、その中で解決する際の優先順位を決めましょう。特に、特定の組織内ではなく、複数の組織にまたがるような課題が効果的です。
ステップ2:スマートファクトリーを実現するツールの選定
スマートファクトリーを実現するためには、デジタル化ツールが必要です。ツールを選定する際には、最初に抽出した課題の中でも優先順位が高いものを解決できるツールを選定することが重要です。もし、自社単独でのツール選定が難しい場合には、この段階で外部の人材に協力を求めるのも効果的な選択肢の一つです。
ステップ3:人材と予算の確保
ツールの導入業務を外部の人材に協力してもらうとしても、そのすべてを任せてしまっては、自社にデジタル化のノウハウが残りません。そのため、社内での窓口となって業務を推進する人材は必要不可欠です。もし、窓口人材を他業務との兼務にしてしまうと、窓口業務が後回しになってしまい、スマートファクトリーの実現がうまくいかない可能性があります。
また、予算の確保も重要です。確保をする際は、スマートファクトリーの遂行中に想定以上の費用が発生するのを防ぐために、投資効果を測る指標を明確にしましょう。
ステップ4:ツールの導入と運用
課題解消のために導入するツールと社内外の人材、予算の確保ができたら、ツールの導入を進めます。初めのうちはツールの機能を絞り、リスクを小さく、費用対効果が大きい箇所からスモールステップで進めていきましょう。実際にツールを運用する中で課題が出てくることが予想されるため、常にブラッシュアップし続けることで効果の最大化を実現できます。
また、導入・運用による効果は、早い段階から従業員全体で共有していきましょう。共有を行うことで従業員のモチベーションを向上させ、デジタル技術を積極的に活用する意識改革が促され、モノづくりとIoTを理解した人材の育成とスマートファクトリーの定着を実現できます。
スマートファクトリーの実現には「生産管理システム」の導入を
メリットの各項目で説明したように、スマートファクトリーを実現するためには、全社的に部門横断で活用できる生産管理システムによりデータを収集・共有し、生産プロセスや計画、進捗状況などを把握することが効果的です。
そこで、大興電子通信が提供する生産管理システム「rBOM」をご紹介します。「rBOM」は、情報をどの部門からでもリアルタイムに管理・共有できる「部品表中心」の統合管理の仕組みであり、スマートファクトリー実現に大きく近づくことが可能です。
スマートファクトリー実現にご関心のある方は、以下のページより資料をダウンロードの上、ご相談ください。
現場からの支持を受けやすい生産管理システムの導入なら生産管理システム「rBOM」
リアルタイムな進捗・原価把握を実現し、スマートファクトリーの実現に効果的な
生産管理システム「rBOM」については、下記よりご覧いただけます。