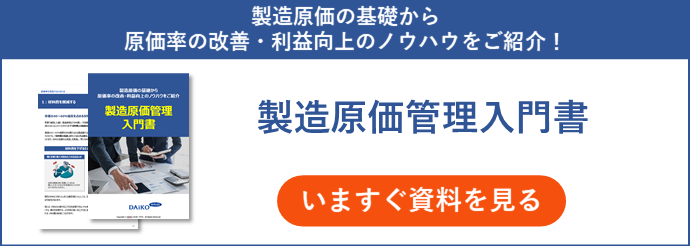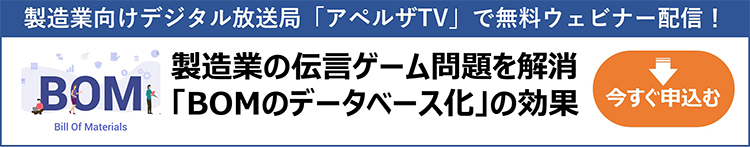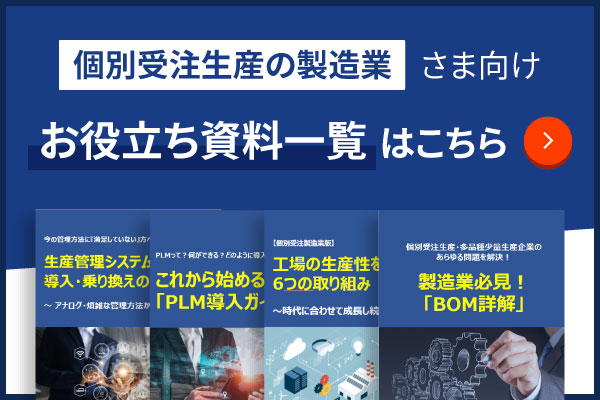原価分析は正確な経営分析を行ううえで必要不可欠です。しかし、原価分析には膨大な手間と時間が必要になるため、実施できている企業は多くありません。
本記事では、経営分析における原価計算の重要性と、その進め方について解説します。
ページコンテンツ
経営分析において重要な「原価計算」とは?
経営分析は会社の財政状況や成績など、自社の現状を客観的に捉えるために非常に重要です。この経営分析を行うためには、原価計算が必要不可欠です。
本章では原価計算とはどういったものか、なぜ原価計算が必要なのかについてご紹介します。
原価は経営分析における粗利益把握のための重要な指標
原価とは自社の製品やサービスを提供するにあたって必要となる費用のことを指し、原価を把握するために原価計算を行います。原価計算を行うことは、製品の販売価格を決定するうえでも、経営計画を立てるうえでも重要です。
経営分析において原価計算が重要となる理由として、粗利益の把握と確保が挙げられます。粗利益を確保することは、商品やサービスの価値を確保することを意味するため、経営を安定させるためにも把握しておきたい指標です。
この粗利益は「売上高-原価」で求めることができますが、原価を算出するためには原価計算が必要となります。
正確に経営分析ができていない企業も多い
粗利益を把握するためには原価計算が必要ですが、原価は材料費だけで構成されるものではないため、計算は簡単ではありません。
原価には材料費や人件費など製品やサービス提供に関する直接費、工場の生産時に発生する電気代や製品塗料・接着剤といった複数の製品やサービス提供にまたがる間接費などが含まれます。これらを把握し正確な原価計算を行うことは非常に難しく、原価計算が困難なために経営分析もできていないといった企業も多くあります。
次章では、原価計算を進めるための方法を3ステップでご紹介します。
どうすれば計算できる?原価計算の進め方
原価計算をするためには、費目別原価計算、部門別原価計算、製品別原価計算という3つのステップを経る必要があります。ここではそれぞれのステップごとの進め方について解説します。
費目別原価計算
原価計算を進めるための最初のステップは費目別原価計算です。費目別原価計算では、製品に必要となる費用を材料費・労務費・経費に大別し、さらに直接費と間接費に分けて計算していきます。
材料費のうち、直接費に含まれるのは「原料費」と「購入部品費」です。
ここでは、製品の元となった原材料や部品に加え消耗品などの費用を計算します。また、外部から購入し、製品に取り付ける部品は購入部品費に割り当てます。間接費には、直接的に製品を製造する際には関わらないものを計上します。具体的には、文房具や手袋など製品の一部にはならないものが該当します。
続いて労務費についてご紹介します。
直接労務費には製品の製造に関わった賃金を計上し、間接労務費には製造に直接関わらない作業が発生した際の賃金を計上します。
最後は経費です。直接経費には、製品の製造に関わる加工を外注したときの費用や金型、治工具が含まれます。また、間接経費には電気やガス代などの光熱費や地代家賃が該当します。
部門別原価計算
次のステップとして、部門別原価計算を行います。
部門別原価計算では、前項でも解説した費目別原価の管理責任がどこの部門にあるのかを明確にします。そのためにも、まずは原価部門を設定する必要があります。
原価部門では、直接製造に関わった製造部門と、直接製造には関わっていないが補助的役割を果たしている補助部門に分類します。そのうえで、先ほど算出した材料費は製造部門に振り分け、労務費は管理部門に振り分けて進めていきます。
全ての費用の責任部門が明確になった後は、最後のステップの製品別原価計算に進みます。
製品別原価計算
最後のステップは製品別原価計算です。
これまでに集計した、材料費、労務費、経費をそれぞれの製品に割り当てていき、製品ごとの原価を計算します。これによって、製品ごとにどれだけ損益があるのかを明確にすることができます。
原価管理のポイントと儲かる会社の作り方についてはこちらの記事もご覧ください。

このような原価計算を行うことで粗利益が求められ経営分析が可能になります。しかし、膨大な情報を収集し計算していく必要があるため、相応の手間と時間がかかってしまいます。このような分析をするためにBI(ビジネスインテリジェンス)を導入している企業も多くありますが、有効に活用できず表計算ソフトで行ってしまっているという企業も少なくありません。
このような事態に陥らないためにも、原価管理を行う原価管理システムの活用をおすすめします。次章では、適切な経営分析を実現する原価計算システムについてご紹介します。
適切な原価計算で正確な経営分析を実現!
原価計算を適切に行えていない場合、経営分析の精度も下がってしまいます。一方で正確な原価計算をするためには膨大な手間と時間がかかることがネックです。
これを解決するのが、販売・生産管理システム「rBOM」と原価分析システム「SHIN」です。
原価管理を実現するシステムを導入するためには、実績をデジタル化する必要があります。大興電子通信の「rBOM」であれば販売や生産に関わるの原価情報を集約することができます。そして、会社全体のお金に関わる情報も集約する「SHIN」と連携することで、強力な原価分析を実現できます。
原価分析システムのSHINには原価分析をわかりやすくする、以下3つの特徴があります。
・販売、生産、購買、会計のデータをもとにSHINでカタチを整える
・データの分析が視覚的に表現することで気づきを得やすい
・1枚で原価・利益の流れを表示、わかりにくい原価計算が概念的に理解できる
これらのシステムを組み合わせることで、経営分析に不可欠な原価計算を手間無く、簡単に実施できます。製品については以下で詳しく紹介していますので、正確な経営分析を行いたい方はぜひこちらもご覧ください。
製造業のデジタル化は大興電子通信にお任せください!
経営分析を実現に欠かせないシステム
「rBOM」と「SHIN」については下記よりご覧ください。