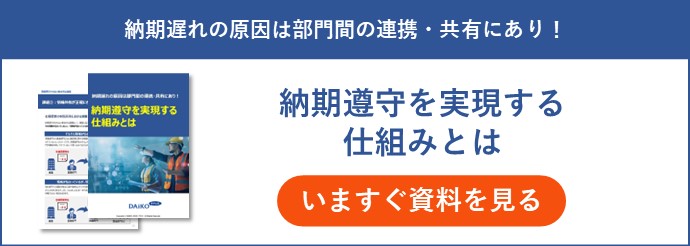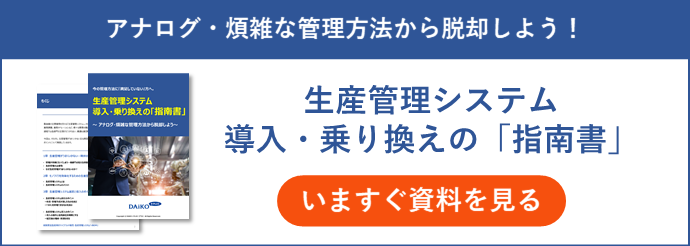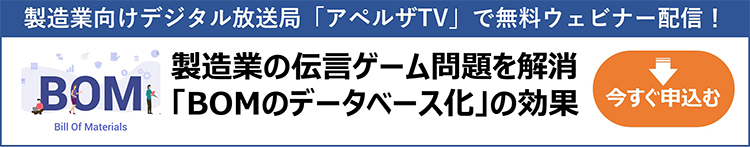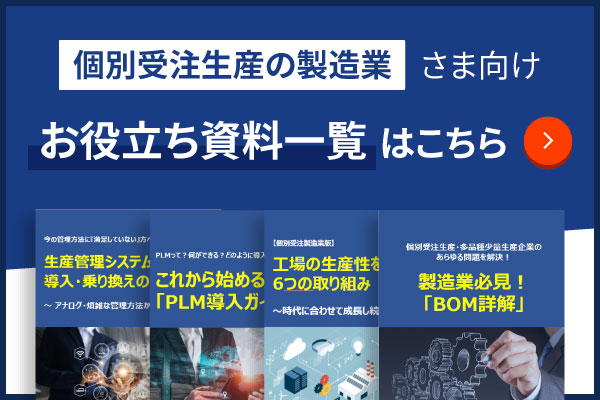生産管理は製造現場だけでなく、製品の生産活動全体に関わる管理業務の総称です。QCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)の最適化や利益向上に直結する重要業務であり、基本をしっかりと理解することが重要です。
本記事では生産管理の基礎から、よくある問題の解決方法まで詳しく解説します。
ページコンテンツ
製造業における生産管理とは

生産管理とは、製品を製造するための資源・手順を調整して、高品質なものを効率的に生産できるよう製造工程を管理する業務全般のことを指します。
具体的には、生産計画の策定・在庫管理・品質管理・進捗管理などの業務が含まれます。
生産管理の目的
大前提として、製造業が利益を最大化させるためには「QCD」の最適化が必要とされています。
生産管理の目的もひとことで表すならQCDの向上です。そのために、前述のように製品を製造するための資源・手順を調整して、高品質な製品を効率よく生産できるように、工程の計画や管理を行っていきます。

生産管理の重要性
製造業において、生産管理の役割は企業経営の観点でも重要な要素です。
製造業が他社との優位性を確立し、市場競争力の強化や利益の最大化といったことを実現するためには、前述のQCDの向上が欠かせません。「高品質なものを・低価格で・短納期で」生産することを通じて利益の最大化を狙うこと、その中枢にあるのが生産管理です。
特に、近年はお客さまのニーズが多様化して同じ製品をたくさん作って安定供給するだけではモノが売れにくい時代になっていたり、人口減少による人手不足でIoT・ITの導入や働き方の見直しが進んでいたりと、製造業を取り巻く状況が大きく変わってきています。こうした業界動向の中で、製造業が市場を生き残るためにますます生産管理の重要性はあがっています。
製造業の業界動向については、こちらの記事で詳しく解説しています。

生産管理と製造管理の違い

生産管理は、生産に関わるすべての活動を総合的に管理することを指し、製造管理も包括します。
その一方、製造管理は現場作業に近い管理を指すことが一般的で、製造現場の進捗を管理する現場監督のような立ち周りが多いです。作業の効率性を高めるだけが目的ではなく、製品の生産数や不良品を出さないように務める品質管理も製造管理の中に含まれます。
このように生産管理は製造管理よりも大きな範囲を管理する点で、製造管理とは意味合いが異なります。
生産管理と工程管理の違い

生産管理は生産ライン全体を総合的な範囲を管理する業務です。一方、工程管理は主に納期を中心とした管理となります。
工程管理では、材料の加工・運搬・検査など、各工程の人員配置や設備の必要数を把握し、適切な振り分けを行うことで製造期間と数量を管理します。
具体的には、管理の進捗状況や生産計画に関する情報を部署間やチーム間で常に共有することで、それぞれの段取りが最適化されます。この結果、作業時間の短縮や製品の過剰生産の抑制が可能となり、コスト削減にもつながります。
製造業における生産管理の具体的な内容

生産管理が担う業務内容は多岐にわたります。
組織体制や企業規模など、企業によって多少異なる場合もありますが、ここでは一般的な業務内容について解説します。
需要予測
市場における自社製品の需要を分析して、必要な生産量を予測する業務です。ここで立てた需要予測をもとに生産量を調整し、供給量のバランスを取ります。
需要に対して供給量が少なすぎれば販売機会を損失しますし、供給量が多すぎれば過剰在庫を抱えることになりムダなコストを生じてしまいます。そこで生産管理担当者は、過去の販売データやこれから受注が決定している案件の情報、市場動向の情報などを分析してなるべく正確な需要予測ができるようにします。
生産計画
需要予測をもとに生産計画を立てていきます。ここでは、何をどれくらい作るのか決めて、必要な資材・設備・人員などを整理し、各工程でどのくらい時間を要するか見立て、受注〜納品までの計画を策定していきます。
どれくらいの供給量を実現するべきか、今いる人員・設備ではどれくらいの供給量をどれくらいの期間で用意できるのか、といった観点を考慮しながら生産計画を立てますが、ここで重要なのはムリ・ムダのない計画を立てていくことです。あまりにムリのあるスケジュールでは品質低下・納期遅延などを起こしますし、ムダの多い計画を立ててしまうと生産能力に対して余力ができすぎてしまったり、過剰在庫を抱えてしまったりとムダなコストを増大させる原因にもなります。

工程計画
生産計画で受注〜納品までの大日程を立てますが、そこからさらに工程を細分化して、より細かい工程計画を立てていきます。ここでは、設計・製造など各工程における具体的な工程を洗い出し、必要な資材・設備・人員の配置から、生産ラインの立ち上げ・稼働や段取り替えなどの各工程にかかる時間を整理して、スケジュールに計画を落とし込んでいきます。
調達・購買計画
必要な資材や備品の調達、および購買を計画する業務です。
何を・いつまでに・どれくらい必要なのか整理して、なるべくコストを抑えながらそれを調達できるよう、サプライヤの選定・交渉などを行っていきます。単に低コストであればよいわけではなく、品質のよい資材を調達できるようにバランスを調整することも非常に大切です。企業によっては、調達・購買部門で担うこともあります。

在庫管理
生産・販売に必要な在庫を適切に調整して、最適化を図る業務です。
欠品や余剰在庫などのリスクを回避して、コストを抑える役割を担います。
何が・どこに・どれくらい在庫としてあるのか在庫を見える化して、在庫の出入りや廃棄などを記録し、正確な在庫状況を把握できるようにします。
品質管理
製造した製品の品質を担保するための業務です。
ロット別・作成日別で製造した製品が、規定の品質を維持できているか管理します。
一般的に、納品前の最終品質チェックは品質管理部門が行いますが、製造のタイミングでの不良品の検知や次工程に渡す前の確認作業などは製造部門が担います。適切に記録・管理を行って顧客満足度の向上やクレームの防止を目指します。
進捗管理
全体の進捗が、計画通りに進行できているか進捗管理する業務です。
もし計画とズレが生じている場合は、計画を見直したり各部門と調整したりして生産計画や納期を守れるよう立ち回ります。進捗に遅れが出た場合は、原因を調査・改善して次の生産計画に反映していきます。
設備・リソース管理
自社で保有している、加工機・道具や冶具・装置などの設備や切削油などの福資材といった、製造に必要な設備・リソース全般の管理・保守を行う業務です。
機器のメンテナンスや消耗品の買い替えなどを行い、製造に必要なリソースを用意します。
以上のように、生産管理には幅広い業務範囲があることがわかります。
また、それらの業務のなかでも、その企業が「受注生産」か「見込み生産」といったオーダー形式や、「ライン生産」「セル生産」「ロット生産」「個別生産」などどの生産形式を採用しているかといった違いによって、生産管理のどの部分に重点が置かれるかも変わってきます。
オーダー形式と生産形式の種類については、以下の記事で詳しく解説しています。

また、生産管理に関するスキル・知識については、こちらの記事も参考にしてください。

スキル・知識・IT活用とは?
製造業が生産管理で抱える問題点

生産管理において、企業では次のような問題点がよくみられます。
1 工程進捗が把握できない
2 設備や担当者の負荷状況がわからない
3 部門ごとに情報がバラバラになっている
4 担当者に属人化している
5 原価集計が煩雑
6 不良やトラブルの発見が遅れる
それぞれ、以下で簡単に解説します。
① 工程進捗が把握できない
計画通りに進んでいるのか、進捗に遅れはないかを把握するためには、作業日報などで進捗把握をしておく必要があります。しかし、製造業では作業日報の作成を手動で行っているところも多く、これが進捗管理の課題になっています。作業日報を作成し、手動でデータ入力をしていると、毎日多くの時間がかかるだけでなく、実績を管理者が把握するまでに書類のプリントアウトや配布、作業員による記録、用紙の回収や集計作業といった工程があるため、リアルタイムで実績の把握ができなくなります。
② 設備や担当者の負荷状況がわからない
実際に生産が開始されると、特定の設備・人員に業務負荷が偏ってしまうことがあります。
しかしこれも、作業日報などのバラバラの情報を見てもひと目でわかるものではないので、把握が難しい状況になりがちです。どこに業務負荷が偏っているのか、反対に余裕があって空いているリソースはどこにあるのか、発生しているムリ・ムダを見える化しない限り、業務負荷を平均化してコスト最適化を図ることができません。
③ 部門ごとに情報がバラバラになっている
昨今では営業や設計、製造など部門ごとに業務の部門最適化が進んでいます。この部門最適化の影響により、部門ごとにExcelで作った管理表や管理のために導入しているITツールが異なるなど、データも部門ごとにサイロ化され新たな問題が生じています。
サイロ化によって発生している問題の1つは、部門ごとに微妙に形式・バージョンが異なるデータが作成されてしまい、どれが最新かわからなくなったり、部門ごとに認識している最新情報が異なったりといったトラブルが発生し得ることです。例えば、部門ごとにBOMデータが複数点在してしまって、仕様変更があったとしてもその情報がタイムリーに伝わらない、各部門がそれぞれのBOMを修正しきれないという問題が発生します。
④ 担当者に属人化している
生産管理の業務は、担当者の属人的なスキル・経験によって回されているケースがよくあります。
ベテランの技術や経験が、標準化・平準化されたりドキュメント化されたりすることなく、組織のノウハウとして蓄積されないまま失われてしまうケースも多いようです。
生産管理の仕事は、その企業のQCDに大きな影響を与えます。限られた人物しか把握できない業務があると、それがボトルネックになって生産工程のスケジュール全体に遅れが生じやすくなったり、需要予測や部門間の連携・調整などの担当者の経験やコネクションに頼っていた部分の業務が滞りやすくなったりします。
特定の人物が出張や欠勤などで現場を外れたり退職したりした場合でも、これまでと同程度以上のQCDを維持できるようにするために、脱属人化が求められています。

⑤ 原価集計が煩雑
原材料費・労務費など、モノを作るためにかかったコストを原価といいます。市場競争を高めるためには、良いものを・安く提供することが欠かせません。安く提供しながらも、十分な利益を出していくためには厳密な原価管理を行っていくことが重要です。
しかしものづくりの現場では、実際に製造をはじめてみると当初見立てた見積原価よりも多くのコストがかかっていたということが起こります。例えば、耐久性・機能性などのテストを行うために試作品を作る過程でかかった原価や、調整・交渉による資材調達費用の変動、不良品やミスによって発生したムダなど、実際原価が変動する因子はさまざまです。
そのため、実際原価を把握するために情報を集めて原価を集計しようとしても、作業がとても煩雑になり、結果的に正しい原価を把握できないという事態になります。
こうした煩雑さゆえに、製造中に「今いくら原価がかかっているのか」をリアルタイムで把握することも難しいので、「製品ができあがってから原価を集計したら、実は原価オーバーで赤字だった」という事態も起こりかねません。

⑥ 不良やトラブルの発見が遅れる
作業日報などの情報からでは工程進捗をリアルタイムで把握することが難しいように、その日に発生した不良・トラブルなどの問題も、管理者がすぐに把握できずタイムラグが生じてしまうことがよくあります。
不良・トラブルの発見が遅れると、生産活動にムダが生じてコストが余計にかかったり、お客さまからのクレームや納期遅延などのより大きな問題に発展したりと、QCDの低下を引き起こします。
問題が発生した際は、何が起きたのかを即座に把握できるようにし、すぐに対策を打って問題の波及を防ぐことが重要です。
また、製造のムダを無くすために不良率管理を行おうとしても、部品・資材の量も膨大で、間にあった工程も複雑なため、どこで不良発生したのかそもそも原因特定が難しいといった問題もよくあります。
製造業の生産管理を効率化する方法

製造業における生産管理は、製品の品質向上、コスト削減、納期厳守など、企業にとって非常に重要な業務です。
しかし、多くの場合は生産管理自体が複雑で時間のかかる作業であり、効率化が課題となっています。
ここでは、製造業の生産管理を効率化する方法について3つのポイントにまとめて解説します。
業務を標準化する
作業手順書を作成して、作業手順を明確化し、誰でも同じ作業ができるようにしましょう。それが業務の標準化につながり、QCDの安定が期待できます。
例えば、作業員によって検査時に見るポイントが統一化されてない場合、製品の品質にバラつきが生じたり、作業ペースが低下したりして進捗が遅れる恐れがあります。
各工程をしっかりマニュアル化することで、品質を維持するだけでなく、作業スピードも上がります。
誰が行っても同じ結果になるよう、作業工程で時間がかかる部分を洗い出すことがおすすめです。
また、マニュアル化が行き届くと、引き継ぎ作業が効率よく行えるため、急な人事異動や人員配置の変更にも対応しやすく、生産ラインを止める心配がありません。
管理データを部門間で共有する
生産管理を円滑に行うためには、在庫データや生産進捗データ、設備稼働データなどの管理データが必要です。これらのデータを部門間で共有することで、全体的な状況を把握しやすくなり、迅速な意思決定が可能です。
部門間の情報共有を効率化してコミュニケーションを促進することも、生産管理体制の強化につながります。日頃から円滑な意思疎通をできる体制を整えましょう。
データ共有に優れたシステムを導入することで、部門間でデータを共有しやすくなり、企業全体の業務データを統合的に管理できます。
ペーパーレス化を図る
製造現場では、多くの情報量を扱っているため、紙媒体のデータ管理では必要な情報の所在が不明確になる恐れがあります。
ペーパーレス化を促進すると、紙の紛失や破損による情報管理上のトラブルを防ぎ、引き出したい情報を見つけやすくなります。
ペーパーレス化の具体例として、書類の承認や回覧を電子化するワークフローシステムが挙げられます。
事例3 原価管理・見積書制作の省力化を実現
株式会社波南様では、自社要件にそぐわない量産型企業向けの生産管理システムを無理やり使っていたために、システムは導入しているものの実態は経理主体でしか使っておらず、実際の生産管理はExcelで処理するという状況が続いていました。
当時は、部材発注のタイミングや発注量は熟練社員の勘に頼りがちで担当者に属人化してしまっていたり、多くの部材が海外から輸入している関係で材料費が為替の変動によって左右され、見積書を何度も作り直す必要があり、作成に時間がかかっていました。
生産管理システム「rBOM」を導入後は、部品表がシステム上で一括管理できるようになり情報の共有化が図られたことで、これまで熟練社員の勘に頼っていた部材発注も、発注の際の基準が明確化されて誰がやってもムダのない業務を行えるようになりました。
また、何度も作り直す必要があるため作成に時間がかかっていた見積書も、原価を入力し直せばその原材料を使用している部品すべての価格が一括変更できるようになったため、作成が早くなりました。
この事例について、詳しくはこちらの記事でご覧いただけます。

製造業が生産管理システムを導入するメリット

生産管理システムを導入することで、従業員の負担を減らすだけでなく、管理面の業務効率が向上したり、あらゆる面でのコスト削減と品質の維持につながったりします。
ここでは生産管理システムの概要に触れつつ、その機能と活用した際のメリットについて解説します。
生産管理システムとは?
生産管理システムとは、製造現場の納期・在庫・工程・コストといったモノづくりの情報を管理するシステムです。製品によって多少異なりますが、部品表、調達資材の手配状況、在庫状況、工程進捗、原価などさまざまな情報を見える化して、生産管理業務を効率化する機能を持っています。
生産管理システムの機能
代表的な機能としては、次のようなものが挙げられます。
・販売管理(受注・売上情報)
・原価管理(見積原価・実際原価)
・部品表管理
・購買管理
・工程管理
・出荷管理
・在庫管理
生産管理システムを活用するメリット
生産管理システムは、上記のような機能を使って次のような利点をもたらします。
■情報の見える化
工程進捗に計画とどれくらい差があるか、資材の手配状況はどうか、現時点でかかっている原価はいくらか、仕様変更や資材変更を経た最新の部品表はどのような状態か…など、生産管理に必要なあらゆる情報を見える化します。これにより、それまで部門間で発生していた問い合わせ作業が要らなくなるなどの業務効率化がもたらされたり、余計なコストがかかっているなどのムダの発見に繋がったりといった利点があります。
■業務効率の改善および生産性の向上
前述の通り、情報が見える化されることで不要な業務を効率化・省力化したり、ムダを発見して生産性を向上したりすることに役立ちます。
また、Excelや紙でのアナログな管理方法から切り替えた場合は、記入ミス・漏れなどの人為的なミスを大幅に削減してくれるなどの利点もあります。
■属人化の解消
需要予測や発注業務など、ベテランの経験・勘に頼って回していた業務をデータとして記録することで、判断基準や運用方法に明確な基準を設け、属人化を解消することに役立つ利点があります。
これから生産管理システムを導入したい方や、今利用しているシステムからの乗り換えを検討したい方は、以下の資料で注意点・導入成功のポイントなどをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
生産管理システムを導入した製造業の問題解決事例

前章でご紹介してきた問題点を、実際に解決している企業もいらっしゃいます。
ここでは、事例を3つご紹介します。
事例1 業務改善・標準化を実現
アイメックス株式会社様では、購買部門がシステム上で入力したデータを他部門が使用するために、一度Excelで作成した管理表に転記する作業が必要でした。この転記作業には膨大な時間がかかっていたうえに、入力ミス・漏れが生じたり、手作業で転記をしているために正確な在庫数を確認できるようになるまでタイムラグがあったりという問題も併発していました。
そこで同社は、システムのリース期限切れのタイミングで新しい生産管理システムの導入を決定。
大興電子通信が提供する生産管理システム「rBOM」に乗り換えをしました。
結果として、これまでのように部門ごとでデータが分断されることはなく、データの一元管理ができるようになったことで転記作業がなくなり、発注作業の時間が1/2以下に短縮できました。
また、入力ミス・漏れも激減してデータの正確性も向上しています。
同時に、これまでは部品の納期を確認するためには部門間で状況確認が行われていましたが、データがシステムに一元管理化されたことで、わざわざ部門間で問い合わせをしなくても、どの部署からも即座に状況を確認できるようになりました。
この事例について、詳しくはこちらの記事でご覧いただけます。

事例2 リアルタイムでの進捗把握・原価把握を実現
神津精機株式会社様では、「リアルタイムな進捗を把握できない」「正確な原価を把握できない」という課題がありました。神津精機株式会社様は多品種少量生産で、一つの商品でも複数の仕様を扱うため、原料となる資材も多様化してしまい原価管理を難しくしていました。また、仕様が確定するまで試作品を作ったりもするので、未使用の材料が出てくるなど、純原価の算出が難しい傾向にあります。
生産管理システム「rBOM」を導入後は、発注した部品・資材などの手配状況や原価をリアルタイムで把握できるようになりました。以前のシステムでは発注業務を行うことはできたものの、「部品が納品されたのか」「社内に在庫があるのか」といった状況をシステム上で確認することはできなかったため、進捗状況をリアルタイムに把握できるようになったことも大きな変化です。
また、従来の方法と比べてシステム入力のミスも削減されたため、出庫のあいまいさがなくなり、原価管理が正確にできるようになったそうです。
この事例について、詳しくはこちらの記事でご覧いただけます。

生産管理システムで製造工程の管理を効率化

ここまで製造業における生産管理について、目的や課題に触れながらご紹介しました。
生産管理システムを導入すると、工程の進捗状況や資材の手配状況などの情報を見える化して部門間で共有できます。業務内容の属人化の防止やトラブル対応の効率化により、生産管理体制の強化につながります。今後、生産管理体制の強化を図りたい場合は、生産管理システムも見直すことも重要です。
製造業の生産管理体制を強化したい場合は、ハイブリッド販売・生産管理システム 「rBOM」がおすすめです。
rBOMは、部品や材料などのリソースを管理し、在庫管理や調達業務の効率化に役立ち、受注から出荷までの情報を部門間でリアルタイムに共有可能にします。